1. �R�`����ڊo�@�y���H�Ɂz

|

|
| ���[�J�[ | �����J�n�N | �傫�� | �d�l�E���l |
|---|---|---|---|
|
���H�� SEIKOSHA |
�吳�T�N�� | �{�̒��a11.5 �p�A�����a�O�D�� |
���������A�ڊo�t �^�J���j�b�P�����b�L�g(Brass Case Nickeled) ���������� ���@�j�~�\�K(�吳�T�N���H�ɃJ�^���O���) |
�Ђ�[�A����Ȃ�������ł��ˁB�w�\�ڂ̏����l�Ƃ�������ł��B �����s�Ŕ����A�������u�Ԃ��爬����߂ĕ����܂���ł����B(��)
����ڊo�͒ʏ�A�x�������v�{�̂ɂ��ꂼ��Œ肳��A��̃x���������Ōq���ł��܂����A����́A ���ʂ̃w�\�ڗp�̂��̂�������߂̃x�����A�䗗�̐^�J���̗��ɌŒ肳��Ă��āA�x���͎��v�ɑ��Ē��݂��Ԃł��B ���͎��v�Ɉ�{�̃l�W�ŌŒ肳��Ă��邾���Ȃ̂ŁA�͂������Ƃ����Ƀx�����������ȕ����������Ă��܂��܂��B
��ʂ̃w�\�ڂ̑ł��ʂ́A�ۂ��`�����Ă��܂����A����͓�̗��@�����߂Ƀn���}�[�̌`�ɂȂ��Ă��܂��B �����U�����́A�MANUFACTURED BY SEIKOSHA,TOKYO,JAPAN��A�吳�T�N�̐��H�ɃJ�^���O�ɂĊm�F�ł��܂����B �Â�����̐��i�Ȃ̂ɃS�g�N�͒����łȂ������̂��A������Ǝc�O�B�@�B�͌��r��Ȃ̂Œʏ�T�C�Y�̋@�B�ł��B (��͏����߂̋@�B�������Ă��܂�)

�n���}�[�`�̑ł��� |
�J�^���O�}��
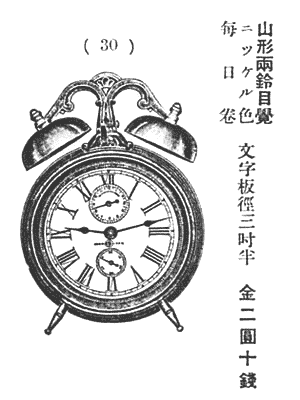
No.899
|
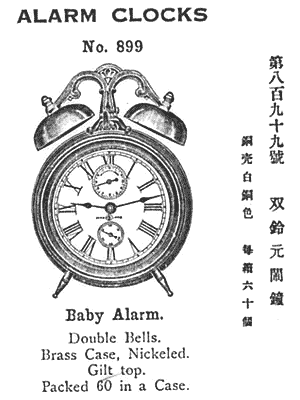
�攪�S��\�㍆
|
�ォ��o��I���

�����͐��̏��W |

���W������Small Movement |
������́A���̎R�`����ڊo�ł��B
�吳9�N�̗A�o�p�J�^���O�����肩��u�hFan�h Mark Small Movement�i���̏��^�w�\�ڋ@�B�j�v���łĂ��܂��B
���J�^���O�ɂ͂܂����̎R�`����ڊo�͏o�Ă��܂���̂Ő��m�Ȑ����J�n�N�͉������炩�͕s���ł����A
���r������̎���̕����V�����̂͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B
�����̎����͂܂��������Ă��܂��A��W�̕����A���p�̏��^�@�B�ŗ���p�̑ŋʕt���A �S���̗��W�A�S���̌��Ƃ����g�ݍ��킹�͐��̓����𑨂��Ă��܂��̂ŁA ���̎R�`����ڊo�����݂������Ƃ͊m���Ǝv���܂��B
PR
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/
7
/
8
/
9
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
�E
����![]()

 �W
�W