2. 呼鈴目覚 初期 【精工舎】
第九ニ四號 呼鈴目覚 ニッケル

|
| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 仕様・備考 |
|---|---|---|---|
|
精工舎 SEIKOSHA |
大正二年頃 |
高 四寸七分 幅 ニ寸六分 金エトウアラビヤ ニ吋 |
毎日巻き、呼鈴付き、ニッケルメッキケース |
呼鈴機能のついた目覚しです。
側は写真のニッケルの他に流金があります。
文字板に精工舎のトレードマークもメーカー名もないのでどこの時計かわからない方が多いようです。
四隅の柱で四方の硝子や板を支える構造で、よくある角型目覚(枕時計)と違ってずっしり重く、
横はガラスでなく不思議な模様の入った金属板。時計のゼンマイを捲く鍵は裏がわにあるのですが、
時計の底には時計のゼンマイよりおおきいベルのゼンマイを捲く鍵がついてます。
目安廻しはヘソ目のものを流用しているものが多いですが、写真の小さなつまみがオリジナルのようです。
また、呼鈴のボタンは中ネジで固定されます。横の板の模様は初期のものほどくっきりしていて、
後期のものはシャープさがないです。たぶん、ひとつの型でいくつもプレスしたのでだんだん型が磨り減ったのでしょう。

|
この特許は明治45年6月21日に「特許権者(発明者)服部金太郎」で出願され、大正2年1月9日に登録されています。
独立した呼鈴機構

ベルのゼンマイは時計のより大きいのが底にある |

|
ベルの機構は一般的な目覚し時計と違い、時計と完全に独立しています。 底にあるゼンマイのトルクは右の写真のように長い軸で上のほうにある呼鈴機構に伝わります。
呼鈴とアラームの仕組み

|

|
ベル(呼鈴)とアラームの切り替えレバーがあり、レバーをベル側にすると右の画像の呼鈴機構最下部にある
カマ状のレバーが時計側についているベルを鳴らす為のアゲバネをロックします。
この状態でベルの上のボタンを押すとゼンマイの力でベルがリン、リン、リン・・・となります。これが
呼鈴です。ベルの状態では目覚しをセットした時間になっても目覚しのアラームは鳴りません。
レバーをアラーム側にすると通常の目覚しと同様になります。
大正2年7月カタログより
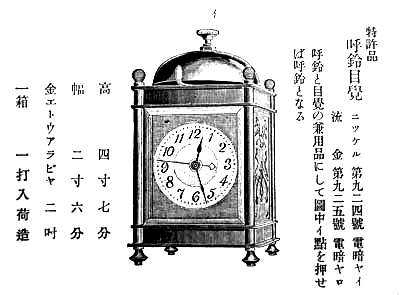
|
第九ニ五號 呼鈴目覚 流金

|
※ この写真の呼び鈴の横板は上下逆さまに組立てられています。
流金タイプ写真提供 いっぽさん
PR
![]() 前頁
・
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/
7
/
8
/
9
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
次頁
前頁
・
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/
7
/
8
/
9
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
次頁![]()
