時計の修理及び掃除が済んだら、組立に取り掛かるのである。
1. 瑞西式龍頭引出剣廻表車龍頭巻装置銘々式
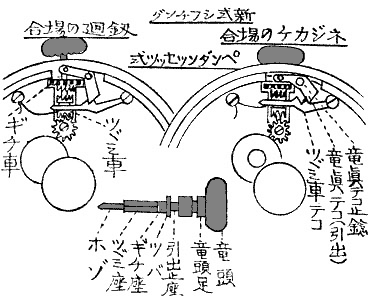
|
右の式に就いて、一通り組立法の説明をなし、他の異なりたる式に就いては、其異なる点のみを説明する。
先ず、ギチ車とツヅミ車とを、龍真に貫いて之を地板の其部に嵌め、ツヅミ車挺を充分に、ツヅミ車中央の凹所に嵌め込み、 此の二つの車を、指にて押さえ、静かに龍真を抜き去る。 之を荒々しく抜いたり、又は抜かずに其儘置けば、ツヅミ車挺が外れて、此の二つの車は離れ落ちる。 間には龍真は抜かずに、其儘置いてもいい様になったのもあるが、之は実地に当たったら直ぐ解る。
実は之より前に、全舞を香箱に嵌め込んで置くのであるが、全舞の入れ方について一通り説明する。 香箱を左手指先にて持ち、右手に全舞の外端五六分許りの所を持って、香箱内の全舞引掛に、全舞の外端を引掛けて少し入れ込み、 直に両手の指先で香箱の下部を支え、両方の拇指を以て、交互に嵌め込んでは押え、嵌め込んでは押えして、 中心に向かって進め入れ込むのであるが、此の両方の拇指は必ず一方の拇指で嵌め込み、確実に押さえ込んでからでなければ、 他の一方の拇指は必ず離してはいけない。 若しも一方の拇指で、未だ確実に押え込まない内に、今一方の拇指を離したら、全舞は強き弾力を以て香箱より飛び出し、 全舞も香箱も共に飛散するから、良く注意してやる。 全舞を全部入れ込んだら、香箱真を入れる。香箱真の引掛が、全舞の中心の切込穴に、確実に嵌まる様にして入れるのであって、 反対に嵌めない様注意せねばならない。 真が入ったら、今度は蓋を嵌め込む。蓋には大概一端に切みがあって、香箱には胴の外に小さき丸形の凹みがある。 之が即ち合印で、之等を同一線上に合わせて嵌め込む。 若しも香箱の胴に、此合印がない時には、香箱の全舞引掛の打込みに合わせる。 若しも之等の合印を無視して、勝手に嵌め込んだら、香箱が真に対して傾き、為に他の歯車や地板或は押等に接触して、 時計の運転を停止する様なことが往々ある。 蓋は香箱の縁より少しも出ない様に、キチット嵌め込まねばならない。 之れで全舞の嵌め込みが完全に出来たのである。
そこで、地板を左指先にて、文字板の方面を下に向けて撮み支へ、ヒゲ箸を右手に持ち、香箱を挟んで、 所定の場所に嵌め込み、次に香箱真を嵌め込む。 龍頭挺のネジと香箱真とが出て居るから、之等を押の所定の穴に入れ、指にて押へと地板との両面より壓して、キチット嵌め込む。 此の際注意を要する事は、ギチ・ツヅミの両車が完全に嵌まって、閂がツヅミ車の凹所に、嵌まって居るか否かと云ふことである。 若しも之等が完全に嵌まって居ない時には、香箱押を少しコヂ開けて、龍真を其二車に通し、閂を嵌め込んでから、 香箱押を押へ込み、然る後之をネジで締め付け、次に全舞巻車を香箱真に嵌めコハゼが、歯と歯の間に嵌まる様にして、 ネジにて締付けるのである。
次に二番車は、取離さず其儘としてあるのであるから、四番車を入れる。(二番車を取離してある時は之を先に) 次に三番車を入れ、二番と三番との押へは、大概一個となって居るから、之を取付けネジにて締付ける。 次に四番及び五番車を前同様にして取付ける。以上各車は、地板及び押のホゾ穴に確実に入れ込んでから、 締付けなければいけないので、若し、万一両方の穴に一方でも入って居ない時に締め付けたら、 ホゾを曲げたり折ったり、又は穴石を破損したりすることがあるから、注意を要する。
伝車の組立が終われば、今度はアンクルの取付けにかかる。 アンクル竿を、下駄歯に近くヒゲ箸にて挟み、地板のホゾ穴に、下ホゾを入れ、アンクル押を取付け、ネジにて締付けるのである。 締付ける前に上ホゾを完全に押のホゾ穴に入れたならば、左示指の先にて、ホゾが抜けない様に、押のホゾ穴の上を押えて居て、 ネジを締付けるのである。若しもホゾが穴より外れて居るのに締付けたなら、殊に此のホゾは小さいのであるから折れ易い。
次には、天府の取付けであるが、之は時計の各部分品の内で、最も取扱いに注意せなければ、破損したり、
時間の調整を狂わしたりするのである。
今迄通り左手指先にて器械を支え、アンクルの方を手前の方に向けて支持する。
そこで右手にヒゲ箸を以て分解の際と同様、確実に天府押を挟み、静かに天府をぶら提げた儘、器械の上に持って来て、
アンクル刺股に、タボ石が入る様にして、天真下ホゾを地板のホゾ穴に嵌め込み、直に押の足を地板の穴に嵌めて、
静かに押に、少しの震動も与えない様にしてヒゲ箸を仕事台の上に置く。
そして右手の加勢を受けて、左手の示指にて、柔らかに天府押の上を押えて、器械を支持する様に、持ち替えたら、
直に右手を放ち、ヒゲ箸を以て天府を静かに動かし、天真上ホゾを押のホゾ穴に入れる。
之がうまく入ったら、左手は其儘外れない様支持して居て、右手拇指の先を、押の足の上部の箇所にあて、
同じく示指と中指を地板裏面にあてて、天真に決して無理せぬ様、足がキチット地板に嵌り込んで、
押と地板が互いに密着する様に、押へ込むのである。
完全に押さえ込んだなら、左手は今迄の様に、やはり示指で押を押えた儘、右手でネジを入れて締付ける。
此のネジを締める時に、注意を要することは、今少しでネジを締付けてしまうと云う時に、左手示指を押より外し、
時計を少し動かして、天府を震動せしめつつ締付けるのである。
天府の震動は、両ホゾが完全に、両ホゾ穴に入って居って、且つ又押がホゾを圧迫して居ないと云う証拠であるから、
若しも天府の震動が其途中に停止する様なことがあれば、直にネジの締め付けを止めて、停止原因を探り、
之を直してから、又天府を震動せしめつつ締付けるのである。
此際、一杯ネジを締め付けたる時に、押が天真を圧迫する様であったら、押のネジより内側に薄い紙片を一枚なり二枚なり、 適宜敷いて締付ける。 其の紙の大きさは、天府輪に触れない位の幅で、長さは押の幅より僅かに短い位にする。 之と反対に天真が短い場合は、足の外側に前同様、紙を適宜敷けば宜しい。 若しも之等の方法を施しても尚ほいけない場合には、取替えるより外に仕方がない。 取替えに就いては改めて講述する。 若しも、筒カナを取外したる場合なれば、天府を取付ける前に、嵌め込んで置く方が宜しい。
天府の取付けが済んだら、文字板の足止ネジが立ネジのものであれば、文字板は後回しにして、器械を側に取付け、 龍真を入れ、機械止ネジ及び龍真挺止ネジを夫々付ける。 龍真挺止ネジを締める時には、挺の足を龍真の凹所に入れて締め付けるので、文字板を先に嵌めてしまえば、 挺の足が龍真の凹所に入り悪いことが往々あるから、其為に文字板を後回しにしたのである。
之れが済んだら、今度は、日裏伝車及び傘車を入れ、文字板を取付ける。 併し、文字板の足止ネジが横ネジ止であったら、器械を側に嵌める前に文字板を取付け、横ネジを完全に締付けてから、 側に入れるのである。 文字板は決してガタ付かない様、確り締付けなければならない。
次に剣を取付ける。其の順序は、時間表示装置の章に於いて述べた通りであるが、剣を押へ込むには、 剣抜箸を使用した方が一番いい。長剣を押へ込む時には、必ず器械表に出て居る二番車を、金敷にあてて居なければならない。 此際注意を要することは、天府押を必ず金敷より、外に外して置かねばならない。 若しも天府押が金敷の上に乗って居たら、天府のホゾを折ったり曲げたりすることが往々ある。 二番真の出方が少なくて、金敷の上に乗せても金敷に達せない様な場合には、先の平面なるタガネを金敷の穴に入れ立て、 此の先に二番真をあてて押え込む。 剣の嵌め込みが済んだら、短剣が一周する迄静かに剣を廻し、剣が文字板又は硝子に或は剣相互が接触することなきやを試す。
次に、両方の蓋をなし全舞を巻いて、時計を表にし裏に返し、種々の方向に傾斜せしめて、之を耳にあて、天府震動の刻音を聞くのである。 如何なる方向に向けても止まらず、且つ其刻音が正確で異常を認めなければ、之でいいのであるから、最後に時間の遅速を試し修正する。 全舞を一杯巻き上げて標準時計に合わせ、十二時間又は一昼夜毎に検査して合わせる。 此際はエボを付して、合わせたる日時分を記入し検査毎に何分進む、或いは何分遅れる(之は一昼夜に何分と云ふ割合に直して記入する)と 云ふ具合に記入して合わせて行く。 正確に合ふ様になったならば正と記入する。 之で全部仕上がったのである。
時間合わせは位置の調整、温度に対する調整を終りたる後、緩急針に依って行ふのであるが、之等は後章にて講述する。 此の時間の遅速合わせは正確にやる程宜しいが、高級の時計は兎に角、普通の安時計では完全に合わせることは、中々困難且つ非常なる手数を要し、 僅かの修理料では到底引き合わないから、一日に一分位の差はいいとして渡して宜しい。 併し、高級時計即ちウオルサム、エルヂン等は合わせるのに左程困難もないから、成可正確にしてやらねばならぬ。 又修理料も高く取って宜しい。修理は十中の九は安時計である。
標準時計としては、ウオルサム又はエルヂン等の高級時計を、正確に正午計にて合わせ備へ置く必要がある。
蓋は嵌めるのに、中々堅いのがある。 蝶番付のものは蝶番の両側より、嵌め込みのものは何れの点からでも良く一方を嵌め込み、 其の両側より両方の拇指にて押さえつつ外側に添ふて前方に同速力にて、両拇指を押し進める。斯くすれば如何に堅い蓋でも嵌る。 硝子を押さえたら破損し易いから、成る可く硝子は押さえない様、縁の外側に添ふて押し進める。
側も磨いてからは、成る可く直接手を触れない様にするのであるが、器械を嵌めこむ際には、絶対手を触れないと云ふことは出来ないから、 器械を入れて蓋をしてから、乾燥せる布片にて良く摩擦して置く。
出典 時計並蓄音機学理技術講義録 大阪時計学院
(大正時代)
