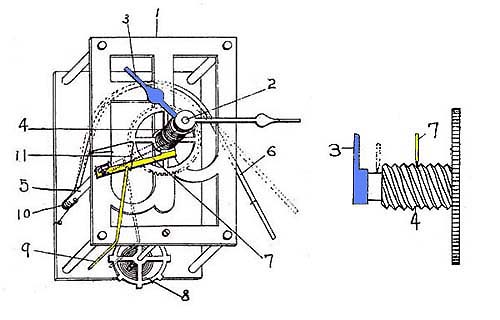3. 木製の貯金時計 【天保銭貯金会】
大正5年頃 天保銭貯金会
木製貯金時計
(浅草茅町 大隅商店製)

|
| メーカー |
製造年 |
大きさ |
仕様・備考 |
|
東京市浅草茅町停留所際 大隅商店
|
大正5年頃
|
高 25.0cm
幅 19.5cm
文字板 四吋
|
毎日巻、天府振、貯金強制装置付、木製
|
この時計は、
前頁の冨士貯蓄銀行の木製貯金時計と仕様がまったく同じです。
裏蓋内には製造元を示すラベルはありませんが、浅草大隅商店製とみて間違いないと思います。
上の銘板に「貯金を休むと時計も休みます」(天保銭と天保銭会のマーク)下に「玉塚翁提案 天保銭貯金会」の銘板あり。
文字板に天保通寶のマーク入り。
機械は精工舎の鍵Sマーク入り、貯金強制装置付ですが特許資料に有る天府に働くストッパー「動杆と制杆」が外されて下の箱の中に入っていました。
一日、コインを投入しない(貯金をしない)とこのストッパーが時計の動きを止める役目をします。
古くは勤勉で貯金箱の流行した時代でしたが、いずれの同様な時計の強制貯金装置が外されているところ見ると、
最初は物珍しく使われてもやがて、時計は時計らしく?働いて貯金まで強制されたくない・・・という結果になったのでしょうか?(笑)
文字板、銘板、他 拡大
天保通宝

|
玉塚翁提案
天保銭貯金会

|
貯金を休むと時計も休みます
天保銭会

|
発明特許
第二四〇七七号

|
機械

|

7 と 9(取り外されていた動杆と制杆)
|
天保銭会と玉塚栄次郎
天保銭会は玉塚栄次郎(明治時代の経済学者)が唱えた贅沢よりも勤勉と貯蓄を重視する生活態度「八分目主義(天保銭主義)」に
共鳴して設立された会で大正5年に発足、本部は神田万世橋畔(東京市神田区竹籠町三丁目)にあった。
PR
 前頁
・
1
/
2
/
3
/
4
/
・
次頁
前頁
・
1
/
2
/
3
/
4
/
・
次頁